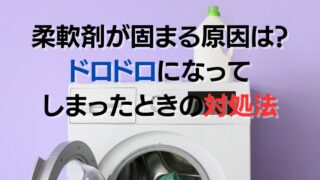 生活お役立ち情報
生活お役立ち情報 柔軟剤が固まる原因は?ドロドロになってしまったときの対処法
柔軟剤は洋服やバスタオルなどをふんわり仕上げるだけでなく、毛玉ができにくくなるため日々使用している人も多いでしょう。 特に冬は静電気防止にもなるため、欠かせないアイテム。 そんな便利な柔軟剤ですが、きちんと管理しないとドロドロになり、固まる...
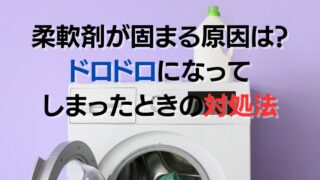 生活お役立ち情報
生活お役立ち情報 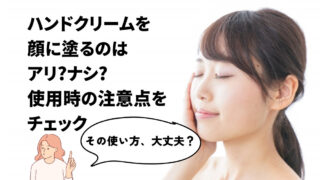 生活お役立ち情報
生活お役立ち情報 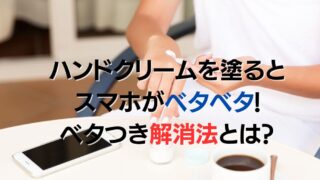 生活お役立ち情報
生活お役立ち情報  生活お役立ち情報
生活お役立ち情報 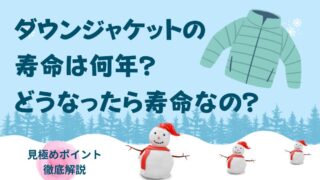 生活お役立ち情報
生活お役立ち情報 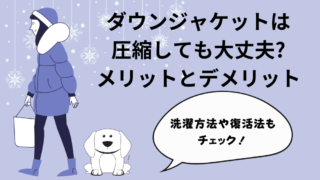 生活お役立ち情報
生活お役立ち情報  生活お役立ち情報
生活お役立ち情報  食品お役立ち情報
食品お役立ち情報  生活お役立ち情報
生活お役立ち情報  生活お役立ち情報
生活お役立ち情報