コロナ禍でおうち時間が増えたことがきっかけで、観葉植物を育てる人が増えました。
最近では100均でも人気種が取り揃えられていて、ミニチュアサイズでも観葉植物が楽しめます。
鉢植えで観葉植物を育てるには、当然土が必要となりますね。
ところで100均の土を使ったら、観葉植物の土からコバエなどの虫がわくなどという話をよく聞きます。
コバエなどの虫がわくと不快なだけでなく、衛生上良くありません。
癒しを求めるはずの観葉植物が、虫のせいでストレスになってしまいます…!
植物にとって土はとても大切。100均の土でなぜ虫がわいてしまうのか、コバエなどがわかないようにするためにはどうすればよいのか。
観葉植物の土の選び方や留意すべきポイントについて解説しますね。
観葉植物の土に100均のものを使うと虫がわいてしまうのか?

100均で購入した観葉植物の土を使ったら、コバエなどの虫がわいたという方が多くいらっしゃるようです。
結論を言ってしまうと「100均で購入した観葉植物の土から虫がわいたことがある」というのは事実です。
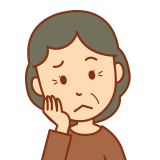
私の友人も悲鳴をあげていました…。
誤解のないように言っておきますが、「それは100均の土だけで、他のお店の土は大丈夫」というわけではありません。
条件さえ整えば、他の観葉植物の土でも虫がわく可能性はあるのです。
けれど観葉植物用の土でも「コバエがわきやすい」ものと「コバエがわきにくい」ものがあります。
どうしてコバエなどの虫がわいてしまうのかを理解して、観葉植物の土を「購入する前に注意・確認すべき点」と「購入した後に虫をわかせないよう注意する点」について解説しますね。
観葉植物の土に100均のものを使うとコバエなどの虫がわくといわれる理由

観葉植物の土に虫がわく原因は、超簡単にまとめると「虫の餌があるから」と「コバエなどの虫にとって生きやすい環境だから」です。
「餌」と言ってしまうと抵抗を感じるかもしれませんが、人間も食べていくために必要なお金を得る「職業」があるところに人は集まります。
「生きやすい環境」の定義は人それぞれかもしれませんが、一般的に生活の利便性が良いところに人は集まりますよね。
虫だって生き物。「餌があり」「自分とわが子が生きやすい環境」をちゃんと選ぶのです。
この条件が揃うと虫は引き寄せられてくるので、虫がわいた!という事態になってしまうのです。
土に虫の餌が含まれている
虫やコバエがわきやすい条件の一つである「餌」とは何か、それは「有機物」です。

有機物って何なの?
光合成によってつくられた「植物の体そのもの(葉や枝)」が有機物であり、その植物と植物の死骸を餌にする「微生物や虫、動物の体そのものとその排泄物と死骸」はすべて有機物です。
虫やコバエがわきやすいと言われる100均の観葉植物の土には共通点があります。「堆肥」あるいは「腐葉土」などの有機物が含まれているのです。
堆肥の原料は、植物性のもの(バーク堆肥とか腐葉土もここに含まれます)と、動物性のもの(主に家畜糞堆肥になります)、あるいはこの混合物から成ります。
あとは食品会社から出てくる食品廃棄物を堆肥にしたものもあります。
つまり観葉植物の土に含まれる堆肥や腐葉土は、「有機物=虫の餌のかたまり」なわけです。
100均の観葉植物の土から虫がわきやすい条件の一つは「虫やコバエの餌」となる「堆肥」や「腐葉土」が含まれているものということになります。
水分が多い
生物が生きていくためには、水は必要不可欠。虫も例外ではなく、小さく弱い虫の幼虫は、水が枯れてしまうと致命的です。
観葉植物の土から発生する不快な虫の代表であるキノコバエは、梅雨時の高温多湿な環境で最も発生しやすいと言われています…。
具体的には気温30℃以上、湿度70%以上がキノコバエの発生条件です。
プランターの土の水はけが悪くて過湿になっていたり、受け皿にいつも水が溜まっているような状態でも過湿になります。
観葉植物を室内でたくさん育てていて、昼間は留守になるので水をたっぷりあげて、暑くなる時間帯は窓を閉めっぱなしとなると部屋の湿度もかなり上がります。
水はけの良い土を使い、プランター間の距離をあけて風通しを良くすることを意識しましょう。
100均の観葉植物の土は虫がわくといわれる理由は他にもある!
虫の餌となる有機物が含まれていて、過湿になると虫がわきやすい条件が整う事は分かりました。
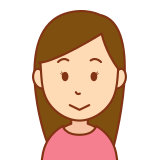
でも、私は有機物が入っている土で観葉植物を長年育てているけど、一回もコバエが発生したことは無いけど…

私は過湿にしてはいけないことは承知しているし、風通しの良い場所にもおいているのに虫がわいた!
そのような場合は、製品の製造場所ですでに卵が生みつけられていて、孵化(ふか)したものであるといえます。
虫やコバエが「その場所を選んで卵を生みつけた」ということは、堆肥を作っている製造場所が虫やコバエに好かれる環境であったということです。
堆肥の製造過程では、発酵温度を60℃以上にして病原菌や雑草の種を不活性化させるという目的があります。この過程で虫の卵や幼虫も死滅します。
ところが水分が多く、堆肥の製造過程(発酵過程)で十分温度が上がっていない状態で長い間おかれると、不快な臭いが発生し、虫をひきよせます。
栄養豊富で、常に水分があり、ほのかに暖かい。虫にとっては最高の環境なのです。
そのような場所で「もわ~っとしたどぶ臭いにおい」がすると、人間が不快と感じる害虫が寄ってきます。
虫は臭いに非常に敏感です。卵を生みつけるのに適した環境であるかどうかは臭いを頼りに集まってきます。
100均の観葉植物の土に含まれている堆肥や腐葉土の質があまりよくないとすると、虫が発生する確率は高くなりますね。
室内専用の有機肥料を販売されている方は、虫の発生にはとても気を使われていて、発酵過程だけではなく、出荷前に再度、人工的に加熱殺菌処理をしています。
堆肥の製造過程をきちんと管理することは、相応の技術とコストがかかります。
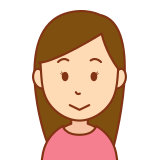
100均での販売価格は1袋100円ですし、原価を考えるとそこまでするのは難しいのかなと感じました。
観葉植物の土に虫が!こんな土は購入を避けるべし!

観葉植物に限らず、○○の専用土として販売されているものは、色々なものがブレンドされています。
品質の悪い「堆肥」や「腐葉土」がブレンドされていると、コバエなどの虫がわきやすいことはご説明しました。
「観葉植物が健やかに育つ土」を作るには、まずはこの堆肥や腐葉土の良し悪しを判断することがポイントです。
このような状態の観葉植物用の土は避けるべき!くわしくご説明していきますね。
- 店頭からすでに袋の周りで虫が飛んでいる土
- 嫌なにおいがする土
- 袋の中で水滴がついている、もしくは塊になっている土
- 袋の中で真っ白なカビがついている土
店頭ですでに袋の周りにコバエが飛んでいる土
まず店頭に並んでいる土を見たときに「袋の周りに虫が飛んでいるもの」は絶対購入しない方が良いですね。
「そんなひどい事があるの⁉」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実際にあるのです。
「重箱の隅をつつく意地悪ばあさん」くらいの心境で「コバエが飛んでいないか?」と意識をして見ないと気付かないかもしれませんが、よく注意して見てください。
虫やコバエは人間よりずっとにおいに敏感です。部屋の中でコバエが発生するような堆肥が発する「かすかに漂う腐った臭い」をかぎつけて集まってきています。
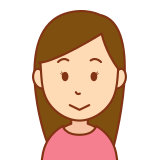
買う前に分かることなので、気を付けて見てくださいね!
嫌なにおいがする土
袋に少し鼻を近づけてみて「嫌な臭いがするもの」は買うべきではありません。
虫やコバエほどではありませんが、人間の嗅覚と本能による判断も侮れないものです。
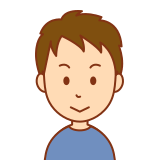
「嫌な臭い」だけでは少し抽象的過ぎますね。もう少し具体的に言うと「モワっ」としたにおいとでも言いましょうか?
「ドブのようなにおい」「少し頭が痛くなるようなにおい」「このにおいで深呼吸はしたくない」と感じたらやめておくべきですね。
ちなみに、良い土や堆肥はよく「土のにおい」とか「森の土のにおい」という表現をされます。森では深呼吸したいですものね。
人間にだって腐ったものを食べないよう、においで判断する能力が備わっています。
人間が「嫌だ」と感じるにおいがするものは、植物も「嫌だ」と感じているといってほぼ間違いないです。
袋の中で水滴がついている&塊になっている土
「袋の内側に水滴がついているもの」「袋の中で堆肥や腐葉土が塊になっているもの」はなるべく避けましょう。
「積み重ねて運搬されれば、圧がかかって塊くらいできるでしょう?」と思われるかもしれませんが、そんなことはありません。
製造過程でしっかり温度があがっていれば、水分も減り、ベタつきがなくなります。
最終的に水分が30%程度まで低下しサラサラとした感触になっていれば、ゴロゴロとした塊はできなくなります。
まだ水分が多い段階で製品にしてしまったものは、袋の中で水滴がいっぱい&塊がゴロゴロできるという事がおこります。室内で虫やコバエがわくリスクがやや高めです!
袋の中で真っ白なカビがついている土
袋の中で真っ白になるほどカビが生えているものはやめましょう。
この手の商品の多くは、裏面の注意書きに「白いものは分解菌(放線菌とか有用微生物と記載されているものもある)なので問題はありません」とか書かれています。
確かに土づくりに有機物と微生物は不可欠で、白い菌は比較的植物の生育にも良いものが多いですが、袋の中で真っ白になるほどカビが生えるのはまだ未熟な堆肥である証拠です。
「未熟な堆肥=やわらかくて食べやすい餌がまだ多く残っている状態」解釈してもよいでしょう。
カビなどの菌が旺盛に繁殖する堆肥は、虫も寄ってきやすいです。キノコバエなどは菌類も餌にしますので、要注意です。
「畑にまいて、混ぜて、しばらく放置してから植え付ける」というくらい、時間的にも場所的にも余裕があれば良いでしょう。
ですが100均など小さなサイズで販売されている土や堆肥を購入する人は、ベランダや室内で気軽に観葉植物を楽しみたい、という人が多いはず。
「虫が嫌だ!」というのであれば、このような商品は購入を避けておく方が無難ですね。
観葉植物に安全なのはこんな土
答えは「上記4つのポイントに該当する堆肥が混ざっている観葉植物の土は使わない」ですが、難しいですよね。
「観葉植物の土」としてすでに色々なものがブレンドされてしまうと、品質が悪い堆肥が混ざっているかどうかは、分かりにくくなります。
微量の嫌なにおい程度なら、炭など消臭効果のあるものと混ぜてしまえばごまかせてしまいます。

ではどうすれば良いのでしょう?
そこでもう1つ「ブレンドされている材料の組成を見て判断する」という方法もあります。
「ヤシガラ(ココピート)」が配合されているのにさらに「堆肥」が混合されているものは、使わない方が良いでしょう。
「ヤシガラ(ココピート)」は炭素が多く窒素が少ないという栄養バランス上、とても分解に時間がかかるという特徴の有機物です。
有機物にはカビが生えやすく虫がわきやすいとお伝えしましたが、ヤシガラ(ココピート)も有機物です。
単体で袋詰めしてある製品であれば、乾いていますし、分解も遅い資材なので問題はありません。
ところが水分が多い堆肥と混ぜて袋詰めされてしまうと、栄養源である窒素と有機物分解菌が入ってしまい、空気の少ないビニール袋の中で微生物分解が進みます。
出荷時、そして顧客が開封した時点で品質が変化する可能性があるので、異なる有機資材を混ぜ合わせるということは普通しません。
- 土(無機物)と堆肥(単品の有機物)の配合ならOK。土と「ヤシガラ(ココピート)」と化成肥料の配合もOK
- 土とヤシガラ(有機物)と堆肥(有機物)のように有機物の資材が2種類入るのはアウト
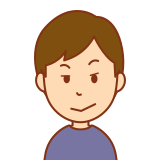
もし後者の組み合わせで製品を作っているとしたら、はっきりいって素人開発品と思われますよ。購入は止めておいた方が良いでしょう。
強いて言うならば、大手の種苗会社とか肥料会社が作っている培養土であれば、大きな間違いは起こらないと認識して良いでしょう。
それが本業だというのに状態の悪い土を売るようなことがあれば、他の商品(種や苗)、ひいては社名に傷がつきますし、ブレンドする素材の品質確認をしている(品質を判断できる人材もいる)からです。
ですのでもちろん、材料の組成が記載されていない商品は論外ですね。
観葉植物のために土づくりをしたい!100均の土でチャレンジ!

観葉植物を単なるインテリアとしてだけではなく、健やかに生長していく過程も楽しみたい、そのためにはちゃんと土づくりをしてあげたいという人もいるはず。
私も色々配合されている土を使ったことがありますが、最終的には「ただの土に勝るものはない」と感じています。
基本は「ただの土」が一番で、そこに「良質な有機物(堆肥)を2割程度混ぜる」です!
使用する土
「赤玉土」や「鹿沼土」を使いましょう。基本は赤玉土、鹿沼土は好きならブレンドする感じです。
余計なものが混ざっていないただの土に、質の良い有機物を1種類だけ使う、これが一番良いです。
「テーブルの上に置けるような小さな植木鉢が1、2鉢あれば良い」と言う人こそ、100均の土はピッタリ。
何といっても1.5リットルというちょうど良いサイズで販売されています。
1、2鉢だと、園芸店で売っている12~14リットルサイズでは大きすぎますしね。
ただし、土だけでは「害もないけど栄養も無い」ので、栄養を補ってあげる必要があります。
ピートモスやヤシガラ(ココピート)は不要
こちらは大きな植木鉢で、どうしても土を軽くしたい、という人は上手に混ぜて使ったら良い、という感じですね。
手で簡単に持ち上げられる程度の小さな植木鉢で育てるなら、このような改良材は不要ですよ。
ピートモスやヤシガラ(ココピート)のような有機質の改良材は、一度乾燥してしまうと、水をはじく性質があります。
土が混ざっておらず、ヤシガラ(ココピート)100%を土のように使う時は特に注意が必要です。
乾いた状態で植木鉢に詰めて、上からジョウロで水を上げるだけでは、なかなか鉢全体に水はいきわたりません。
鉢の中で水の通る道ができてしまうと、水はそこばかり流れて鉢の下から水が出てくるようになってしまいます。
「鉢の下から水が出てきたし、たっぷりお水を上げたわ!」などと思っていると、実は見えている部分だけが濡れていて、鉢の中全体はカラカラということになっています。
有機質の改良材だけでなく、培養土でも有機質の配合割合が高くて軽いものは、同様に注意してくださいね!
土だけでどうやって水はけや水持ちを確保するか
水はけを良くするためにはパーライトを入れ、水持ちを良くするためにはピートモスやヤシガラを入れ…とよく言われますが、土の粒の大きさを調整するだけで十分です。
「赤玉土はちょうどよい水持ち」がもともと備わっているのですが、大きすぎる粒ばかりになると水はけは良いですが、水持ちが悪くなります。
そして逆に、粒が小さすぎると目詰まりを起こしやすくなります。
私の経験上になりますが、小さな植木鉢で育てる場合の、一番良かったと思う粒の大きさは次の通りです。
イメージで言うなら「鉢底ネットの網目にぎりぎり引っかかって落ちてこない粒の大きさ」です。私は以下のように調整しています。
大きすぎる粒を取り除く
3~5mm以上の大きな粒は、ふるいにかけて取り除きます。「それじゃほとんど取り除かれちゃうよ!」という場合は、軽くつぶして細かくしてください。
潰すと粉のように細かくなってしまうものも出てきます。
細かすぎる土を取り除く
次は「細かすぎる土」を取り除きます。料理で小麦粉を振るったり、裏越しに使うような目の細かいふるいを使うと良いでしょう。
小さな植木鉢に使うなら、3mm以下に調整したものが向いています。
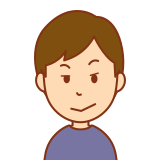
植木鉢のサイズが大きければ5mm以下でも許容範囲って感じですね。
好みで鹿沼土と混合しても良いかと思います。ちなみに何年か前までは、細粒赤玉土というのがありました。
とても使い勝手が良かったのですが、最近は中粒と大粒しか見かけません。
生産するときに歩留まりが悪いから、採算が合わなくて無くなってしまったのかもしれませんね。
本当に欲しい良質な有機物とその混合量の目安
土の準備ができたら、有機物を1~2割混合します。腐葉土や完熟堆肥ですね。
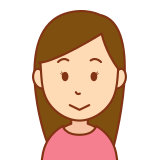
この有機物が一番の問題ですね。何といっても虫が湧く原因となりかねませんから!
植物も根を伸ばし、古くなった根は枯れて土に返ります。そのとき、微生物の働きがないと、いつまでも分解されず、やがて病原菌や腐敗菌の温床になっていきます。
植物を健やかに育てるには、植物の掃除役を果たしてくれる微生物とその餌や棲み家となる有機物が必要です。
使用料ですが、袋の裏の成分表を見て「3%以上窒素が含まれているなら混合量は1割」まで、「1.5%以下なら2割は混合する」を目安にしましょう。
でも、完熟たい肥といって販売していても、実際は完熟じゃないものがあったりするので紛らわしいです。
じゃ、どれを買えば良いの?というのが実情ですが、よくわからないなら自分で作るのもアリです!
次に、良くない発酵堆肥を叩きなおして良い状態にしてしまう方法もご紹介しますね。
100均の発酵堆肥を良質堆肥に変える方法

今手元にある有機物(堆肥や腐葉土)は使えるのか
「観葉植物に使わない方が良い土」のところでも説明しましたが、「嫌なにおい」がしないものであればおおよそ大丈夫です。
もっと確実に判断するならば、堆肥をペットボトルに入れて水につけ、ふたをした状態で日の当たる(暑くなる)場所に2~3日置いてみてください。
真っ黒になったり、ヘドロのような臭いがするものは使わない方が良いでしょう。
袋の中でカビのような菌が生えていたとしても、嫌な臭いがしないのであれば少し手を加えて使用可能です。
コバエが飛ぶ100均の発酵堆肥を良質堆肥に変える方法
本来、製造段階で60℃以上の温度が数日以上維持されていれば、あまい発酵臭を発生する「善玉菌」が大部分を占める堆肥が出来上がっています。
そうであれば不快な虫は寄ってこないはず。ですがすでに虫の卵が産みつけられている可能性があるので、自分で加熱処理してしまいましょう!
土を拡げて日に当てる乾燥方法が紹介されていたりしますね。
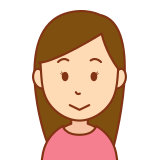
私は一旦、袋のまま真夏の灼熱のベランダに数日間放り出します!
ベランダの素材がアルミなどの金属製であれば、その上に直接置きます。
自分は裸足では歩けない、手で触れないというような熱さに、堆肥の中の虫や卵を曝してやろう!作戦というわけです。
ですのでアルミバットや捨てようと思っていた壊れた鍋、熱伝導の良い金属製のものがあれば、ここで活用しちゃいましょう。
そんなものあった?という感じですが、我が家には壊れた炊飯器の中のカマがあります。母が勿体ないといって捨ててくれないので!
袋にハエが寄ってくるようならビニール袋に堆肥の袋ごと放り込んで密封しておきます。
これで大体、嫌な臭いを発してものを腐らせるような微生物(病原菌も含まれます)と虫の卵と幼虫は死に絶えます。
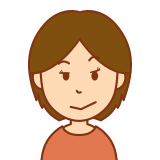
よほどひどい堆肥でない限り、「どぶ臭いにおい」が、「あまい発酵臭」に変わりますよ。
ちなみにダイソーで買った「発酵堆肥」(茶葉やコーヒーを原料にして作った堆肥)は、購入したままではコバエが寄ってきましたが、この方法で甘い匂いがする堆肥に変わりました。
甘い匂いに変わったら、過剰な水分を少し飛ばして、サラサラに仕上げてから使います。
観葉植物は土を使わないタイプもある!100均でも購入可能

観葉植物を育てるのに、そもそも土や堆肥を使わなければ、虫への心配は無くなります。
小さな部屋で、ほんの一鉢だけ育てたいだけ、というのであれば、このほうが良いですね。
ダイソーの店頭では、写真のように水だけで育てられる観葉植物もあります。水も土もいらない「エアプランツ」ですね。

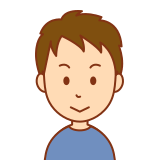
ただ、時々霧吹きで水を吹き付けて、水分補給をしてあげましょう。
ハイドロボールを使った水耕栽培などもありますよ。ハイドロボールは、中粒より小粒のほうがおすすめです♪

まとめ

- 観葉植物の土は100均のものだけではなく、条件さえ整えば他の土でも虫がわく可能性がある
- 観葉植物の土にコバエなどの虫がわく原因は、虫の餌となる「堆肥」あるいは「腐葉土」などの有機物が含まれているから
- 観葉植物のプランターの水はけが悪くて過湿になっていたり、受け皿にいつも水が溜まっているような状態も避けるべし
- 堆肥の製造過程(発酵過程)でも十分温度が上がっていない状態で長い間おかれると、臭いが発生して虫をひきよせることになる
- 店頭からすでに袋の周りで虫が飛んでいる土、嫌なにおいがする土、袋の中で水滴がついている、もしくは塊になっている土、袋の中で真っ白なカビがついている土は使わないようにする
- 観葉植物にとって良い土の見分け方は、ブレンドされている材料の組成を見て判断するという方法がある。ヤシガラ(ココピート)に堆肥が混ざっているものは使わない方が良い
- 観葉植物に100均の土を使う際は、赤玉土や鹿沼土を使い、腐葉土や完熟堆肥などの有機物を1~2割混ぜるのが良し。粒の大きさをふるいにかけて調整すると水はけ・水持ちが向上する
- 観葉植物用の土を良質なものに変えるには、自ら加熱処理すると良い!熱伝導に優れた金属を使って日に当てるのがおすすめ!
- 100均では、土を使わないエアプランツやハイドロボールを使った観葉植物も購入できる
私は良い堆肥を作っている人から直接分けてもらえるという幸運な特権を手にしましたので今は市販品を買うことが無くなってしまいましたが、土づくりは難しいですよね。
健やかに育った観葉植物は、おうち時間において癒しでもあるはず。
観葉植物にコバエなどの虫がわいて逆にストレスが増えないように、100均の土であったとしても上手く活用していきましょう♪



コメント